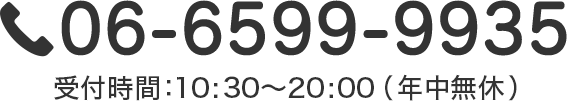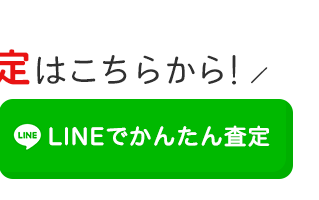〒556-0005
大阪市浪速区日本橋4-11-10 大南ビル1階
これで安心!スマホの防水性能 完全ガイド|規格(IPX)・おすすめ機種・水没対策

スマートフォンの「防水」性能、どこまで信用していますか。
お風呂や雨の日でも安心して使いたいですよね。
この記事では、防水性能を示すIPX規格の正しい見方から、利用シーンごとの注意点、最新のおすすめ機種情報、万が一の水没時の対処法まで、スマホの防水に関する疑問を徹底解説します。
防水性能を過信せず、正しい知識を身につけて、大切なスマホを水のリスクから守りましょう。
1. スマホの防水性能を示す「IPX」とは?基本を解説
スマートフォンを選ぶ際、カメラの性能やバッテリーの持ちと並んで、多くの方が気にするのが「防水性能」ではないでしょうか。
特に日本では、お風呂でのリラックスタイムに動画を見たり、キッチンでレシピを確認したり、あるいは突然の雨に見舞われたりと、スマートフォンが水に濡れる可能性のあるシチュエーションは少なくありません。
そんな時、頼りになるのがスマホの防水性能です。
しかし、スペック表などで「IPX8」や「IP68」といった表記を見ても、具体的にどの程度の性能なのか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
この章では、スマートフォンの防水性能を理解する上で欠かせない「IPX」という規格について、その基本的な意味や見方、そして混同しやすい防塵性能との関係などを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
ご自身のスマホ選びや、今お使いのスマホをより安心して使うための知識として、ぜひ参考にしてください。
1.1 防水等級IPXの意味と見方
スマートフォンのスペック表や製品紹介で頻繁に目にする「IPX●」(●には数字が入ります)という表記。
これは、国際電気標準会議(IEC)によって定められた、電気製品の防水性能に関する保護等級を示す国際規格です。
日本でもこの規格は、JIS(日本産業規格)C 0920として採用されており、国内で販売される多くのスマートフォンがこの基準に則って防水性能を表示しています。
「IP」とは「Ingress Protection(イングレス プロテクション)」または「International Protection(インターナショナル プロテクション)」の略で、「侵入に対する保護」という意味を持ちます。
そして、「IP」に続く「X」の部分に入る数字(0から8までの9段階)が、水の侵入に対する保護の度合い、つまり防水性能のレベルを示しています。
数字が大きければ大きいほど、より高い防水性能を持っていることを意味します。
それぞれの等級は防水性能の内容が異なるため、複数の項目に合格しているという意味で等級が併記されることもあります。
例えば、「IPX7」と表記されていれば、そのスマートフォンは防水性能の等級が「7」であることを示しています。
「X」の部分は、通常は防水性能の等級が入りますが、もし防水性能の試験が行われていない、あるいは規定されていない場合は「X」と表記されることもあります。
1.2 IPXだけじゃない 防塵性能を示すIP等級との関係
スマートフォンのスペックを見ると、「IPX8」のような表記だけでなく、「IP68」のように「IP」の後に2つの数字が並んでいるケースが多いことに気づくでしょう。
これは、「IP等級」が本来、防水性能だけでなく、固形物の侵入に対する保護、すなわち「防塵性能」も示す規格だからです。
「IP●△」という表記において、最初の数字「●」が防塵性能の等級を、2番目の数字「△」が防水性能の等級を示しています。
防塵性能は、0から6までの7段階で評価され、数字が大きいほど、人体や固形異物(チリやホコリなど)の侵入に対する保護レベルが高くなります。
最高等級である「6」は、「粉塵の侵入が完全に防護されている」状態、つまり「完全防塵」を意味します。
したがって、「IP68」と表記されているスマートフォンは、最高レベルの防塵性能(IP6X)と、非常に高い防水性能(IPX8)の両方を兼ね備えているということになります。
スマートフォンは精密機器であり、ホコリや砂なども故障の原因となり得ます。
アウトドアでの利用や、ポケットやバッグに入れて持ち運ぶ際など、ホコリっぽい環境にさらされることも少なくありません。
そのため、防水性能(IPX)だけでなく、防塵性能を示す最初の数字も合わせて確認することで、より総合的な耐久性を把握し、安心してスマートフォンを使用することができます。
1.3 防水性能の等級ごとの違い IPX5 IPX7 IPX8を比較
防水性能を示すIPXの等級は、0から8までありますが、スマートフォンのスペックとしてよく見かけるのはIPX5、IPX7、IPX8あたりです。
これらの等級が、具体的にどの程度の水の侵入に耐えられるのか、その違いを見ていきましょう。
IPX5:噴流水に対する保護
- 定義:「あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を受けない」レベルです。
- 具体例:水道の蛇口から出る水(流水)や、シャワーの水しぶき、やや強めの雨などが該当します。キッチンやお風呂場での軽い水はね程度なら耐えられる性能と言えます。
- 注意点:水の中に沈めること(水没)は想定されていません。
IPX7:一時的な水没に対する保護
- 定義:「一時的に一定水深(通常は1m)の条件で水没しても内部に浸水しない」レベルです。
- 具体例:うっかりトイレや洗面台、お風呂の浴槽などに落としてしまった場合でも、すぐに拾い上げれば浸水による故障のリスクを低減できます。
- 注意点:定められた時間(通常30分間)と水深(通常1m)を超える水没や、水中でスマートフォンを操作することは保証されていません。
IPX8:継続的な水没に対する保護
- 定義:「IPX7よりも厳しい条件下で継続的に水没しても内部に浸水しない」レベルです。IPXの防水等級としては最高レベルにあたります。
- 具体例:メーカーによって具体的な保護の条件(水深や時間)は異なりますが、一般的にIPX7よりも深い水深や長時間の水没に耐えうる性能を持ちます。(例:「水深1.5mに30分間沈めても動作に問題がない」など)
- 注意点:これもメーカーが定める条件内での保護であり、水中での使用を推奨するものではありません。また、海水や温水、石鹸水など、真水・常温水以外の液体に対する耐性は保証されていない場合がほとんどです。
このように、IPXの等級によって保護される水の状況は大きく異なります。
日常生活での雨や水しぶきへの対策としてはIPX5以上、万が一の水没事故に備えたい場合はIPX7以上が一つの目安となるでしょう。
現在販売されている高性能なスマートフォンの多くはIPX8に対応しており、より安心して使えるようになっています。
1.4 自分のスマホの防水性能を確認する方法
今お使いのスマートフォンや、これから購入を検討している機種が、どの程度の防水・防塵性能(IP等級)を持っているのかを知りたい場合、いくつかの確認方法があります。
主な確認方法は以下の通りです。
- メーカー公式サイトの製品ページを確認する:
これが最も確実で、最新かつ詳細な情報が記載されています。各メーカーのウェブサイトにアクセスし、該当するスマートフォンのモデル名で検索して、「仕様」「スペック」「技術仕様」といった項目を確認しましょう。IP等級が明記されているはずです。 - 取扱説明書を読む:
スマートフォン購入時に同梱されている取扱説明書にも、IP等級に関する記載がある場合があります。「安全上のご注意」や「主な仕様」などのセクションを探してみてください。 - スマートフォンの設定メニュー内を確認する(機種による):
一部のスマートフォンでは、「設定」アプリの中から端末情報を確認する過程で、認証情報などと共にIP等級が表示される場合があります。例えば、「設定」>「端末情報」>「認証」や「設定」>「デバイス情報」>「法的情報」といった項目を探してみると見つかるかもしれません。(メーカーやAndroidのバージョンによってメニュー構成は異なります)
これらの方法の中でも、最も手軽で確実なのは、やはりメーカーの公式サイトで確認することです。
中古でスマートフォンを購入する場合など、説明書や箱が手元にない状況でも、モデル名さえわかればインターネット経由で簡単にスペックを調べることができます。
ご自身のスマートフォンの性能を正しく把握し、適切な使い方を心がけることが、水濡れによるトラブルを防ぐ第一歩となります。
2. スマホの防水性能に関するよくある疑問と注意点
スマートフォンの防水性能は非常に便利ですが、その能力を過信すると予期せぬトラブルに見舞われることもあります。
ここでは、スマホの防水性能に関するよくある疑問や、使用上の注意点について詳しく解説します。
正しい知識を身につけ、大切なスマホを水のリスクから守りましょう。
2.1 お風呂でスマホを使っても大丈夫?
多くの防水スマホはIPX7やIPX8といった高い防水等級を備えていますが、これらは基本的に常温の真水に対する性能を示しています。
お風呂のような高温多湿な環境での使用は想定されていません。
湯気は細かい水の粒子であり、防水規格で防げる想定の水の侵入とは異なる形で内部に入り込む可能性があります。
また、急激な温度変化はスマホ内部に結露を発生させる原因にもなります。
さらに、シャンプーや石鹸、入浴剤などが含まれたお湯は、真水とは異なる性質を持っており、防水パッキンや端末のコーティングを劣化させる恐れがあります。
これらの理由から、防水性能が高いスマホであっても、お風呂での積極的な使用は推奨されません。
どうしてもお風呂で使いたい場合は、専用の防水ケースに入れるなどの対策を検討しましょう。
2.2 海やプールでの使用は?海水や塩素水の影響
お風呂と同様に、海やプールでの使用も注意が必要です。
IPX等級は真水での試験結果であり、海水やプールの水(塩素水)に対する防水性能を保証するものではありません。
海水に含まれる塩分は、スマートフォンの金属部分(充電端子など)を腐食させる大きな原因となります。
腐食が進むと、充電ができなくなったり、接触不良を起こしたりする可能性があります。
一方、プールの水に含まれる塩素(次亜塩素酸)は、防水のために使われているゴム製のパッキンやシールの劣化を早める可能性があります。
防水性能が低下し、水没のリスクが高まります。
万が一、海水や塩素水にスマホが触れてしまった場合は、速やかに常温の真水で洗い流し、柔らかい布で水分を拭き取ってから、十分に自然乾燥させることが重要です。
しかし、基本的には海やプールでのスマートフォンの使用は避けるべきです。
2.3 スマホの防水性能は時間とともに劣化する?
はい、スマートフォンの防水性能は永続的なものではなく、時間とともに劣化する可能性があります。
防水機能は、本体内部への水の侵入を防ぐために、ゴム製のパッキンや特殊な接着剤(シール材)によって維持されています。
これらの部品は、紫外線や温度変化、経年劣化によって硬化したり、弾力性を失ったりすることがあります。
また、スマートフォンを落とした際の衝撃や、本体の歪みなども、部品の間に隙間を生じさせ、防水性能を低下させる原因となります。
バッテリー交換などの修理で本体を分解した場合も、再組み立ての際に新品時と同等の防水性能が維持されない可能性があります。
中古のスマートフォンを購入する場合も、以前の使用状況によっては防水性能が低下している可能性があるため注意が必要です。
防水性能を長持ちさせるためには、丁寧な取り扱いを心がけ、極端な温度変化や衝撃を避けることが大切です。
2.4 防水スマホでも水没することがある理由
高い防水等級を持つスマートフォンでも、水没してしまうケースは存在します。
その主な理由は、防水性能の限界を超えた状況で使用してしまうことです。
例えば、IPX7は「水深1mに30分間沈めても浸水しない」ことを意味しますが、それ以上の水深や時間、あるいは強い水圧(例:水道の蛇口から勢いよく水をかける)がかかると、水が内部に侵入する可能性があります。
また、前述の通り、経年劣化や衝撃による防水性能の低下も水没のリスクを高めます。
さらに、意外な見落としとして、SIMカードトレイやUSBポートのキャップ(キャップ式の場合)が完全に閉まっていない、または緩んでいる場合も、そこから水が浸入する原因となります。
キャップレス防水の機種でも、端子部分に水分や異物が付着したまま充電すると故障の原因になることがあります。
「防水」は「完全防水」ではないという認識を持ち、メーカーが想定する使用範囲を守ることが重要です。
2.5 防水ケースは必要?選び方のポイント
スマートフォンの防水性能だけでは不安な場合や、お風呂、海、プール、スキー場など、より積極的に水辺や湿度の高い場所でスマホを使用したい場合には、防水ケースの使用が有効な対策となります。
防水ケースを選ぶ際には、まずケース自体の防水性能(IPX等級)を確認しましょう。
使用したいシーン(例:お風呂での動画視聴ならIPX6以上、水中に沈める可能性があるならIPX8)に合わせて適切な等級のものを選ぶことが大切です。
また、自分のスマートフォンに対応したサイズ・機種であるかを必ず確認してください。
ケースに入れた状態での画面のタッチ操作やサイドボタンの操作がスムーズに行えるかも重要なポイントです。
その他、密閉方式(ジッパー式、ロック式など)、素材の耐久性、ネックストラップの有無、水に浮くフローティング機能なども考慮して選びましょう。
購入後は、実際にスマホを入れる前に、ティッシュなどを入れて水に沈め、浸水しないかテストすることを強く推奨します。
ただし、防水ケースも万能ではなく、破損や閉め忘れがあれば浸水する可能性はありますので、過信は禁物です。
3. 【2024年版】防水性能が高いおすすめスマホ機種
スマートフォンの防水性能は、日常生活での安心感を大きく左右する重要な機能の一つです。
特に近年発売されるスマートフォンの多くは、高い防水性能を備えています。
この章では、2024年現在、特におすすめできる防水性能の高いスマートフォン機種を、iPhoneとAndroidに分けてご紹介します。
機種選びの際には、防水等級「IPX」だけでなく、防塵性能を示す「IP」等級全体や、ご自身の使い方に合った性能かどうかを確認することが大切です。
3.1 iPhoneシリーズの防水性能とおすすめモデル
iPhoneは、比較的早い段階から防水性能に対応してきました。
特に近年のモデルでは、高い防水・防塵性能であるIP68等級が標準となりつつあります。
ここでは、最新モデルと、中古市場でも人気の高いモデルの防水性能について解説します。
3.1.1 iPhone 16シリーズの防水性能
2024年発売のiPhone16シリーズ(iPhone 16,iPhone 16 Plus,iPhone 16 Pro,iPhone 16 Pro Max)は、全モデルでIP68等級の防水・防塵性能を備えています。
これは、IEC規格60529に基づき、「最大水深6メートルで最大30分間」の耐水性能を持つことを意味します。
日常生活における雨や水しぶきはもちろん、うっかり水の中に落としてしまった場合でも、すぐに拾い上げれば問題ないレベルの高い性能です。
ただし、Appleの保証は水濡れによる損傷をカバーしていない点には注意が必要です。
過信せず、故意に水に浸けるような使い方は避けましょう。
3.1.2 中古で狙い目?iPhone SE(第3世代)の防水性能
比較的手頃な価格帯で購入できるiPhone SE(第3世代)も、防水性能を備えています。
こちらのモデルはIP67等級の防水・防塵性能に対応しています。
IP67は「最大水深1メートルで最大30分間」の耐水性能を示します。
iPhone 16シリーズのIP68には劣るものの、日常生活での水濡れリスクに対しては十分な保護性能と言えるでしょう。
コストを抑えつつ防水性能のあるiPhoneを探している方にとって、中古市場も含めて魅力的な選択肢となります。
ただし、中古品の場合は経年劣化により防水性能が低下している可能性も考慮しましょう。
3.2 Androidスマホのおすすめ防水モデル
Androidスマートフォンは、メーカーやモデルによって防水性能への対応状況が異なります。
しかし、近年ではハイエンドモデルだけでなく、ミドルレンジのモデルでも高い防水性能を備える機種が増えています。
ここでは、主要なAndroidスマートフォンメーカーのシリーズごとの防水性能と特徴を見ていきましょう。
3.2.1 Google Pixelシリーズの防水性能
Google Pixelシリーズは、高性能なカメラとAI機能で人気のスマートフォンです。
フラッグシップモデルであるPixel 9 ProやPixel 9は、IP68等級の高い防水・防塵性能を備えています。
ミドルレンジモデルのPixel 8aなどもIP67等級に対応しており、幅広い価格帯で防水性能を持つモデルが選択可能です。ただし、Pixel 9 Pro FoldはIPX8で防塵機能がないため注意が必要です。
最新のAI機能と安心して使える防水性能を両立したい方におすすめのシリーズです。
3.2.2 Xperiaシリーズの防水性能
ソニーのXperiaシリーズは、古くから防水性能に力を入れてきたメーカーとして知られています。
現在のフラッグシップモデルであるXperia 1シリーズやXperia 5シリーズは、IP68等級の優れた防水・防塵性能を誇ります。
これらのモデルは、高品質なカメラやディスプレイ、オーディオ機能に加え、高い防水性能を両立している点が魅力です。
ミドルレンジのXperia 10シリーズなどもIP68に対応しており、幅広いニーズに応えるラインナップとなっています。
3.2.3 AQUOSシリーズの防水性能
シャープのAQUOSシリーズは、国内メーカーならではの機能と使いやすさで人気です。
多くのモデルが防水・防塵性能に対応しており、フラッグシップのAQUOS Rシリーズはもちろん、人気のミドルレンジモデルであるAQUOS senseシリーズもIP68等級の防水・防塵性能を備えています。
「お風呂対応」を謳うモデルも多く、日本のユーザーのライフスタイルに合わせた防水設計が特徴と言えます。
ただし、お風呂での使用には注意点もあるため、取扱説明書をよく確認しましょう。
3.2.4 Galaxyシリーズの防水性能
サムスンのGalaxyシリーズは、世界的に高いシェアを持つ人気のスマートフォンです。
フラッグシップモデルのGalaxy Sシリーズは、最新モデルでIP68等級の高い防水・防塵性能を備えています。
また、近年注目されている折りたたみスマートフォンのGalaxy Z FoldやGalaxy Z Flipシリーズも、IPX8等級の防水性能に対応しており、技術的な進化を見せています(防塵性能は非対応の場合あり)。
ミドルレンジのGalaxy Aシリーズの一部モデルも防水に対応しており、デザインや性能、価格帯に応じて多様な選択肢があります。
3.3 コスパ重視派向け 防水性能付きスマホの選び方
最新のハイエンドモデルでなくても、十分な防水性能を持つスマートフォンは数多く存在します。
コストパフォーマンスを重視して防水スマホを選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。
まず、必要な防水等級を確認しましょう。
日常生活での雨や水しぶき、軽い水没程度であれば、IPX7等級でも十分な場合があります。
より安心感を求めるならIPX8等級が望ましいでしょう。
次に、型落ちモデルを検討するのも一つの方法です。
1~2世代前のハイエンドモデルやミドルレンジモデルは、性能が高く、かつ価格が手頃になっていることがあります。
これらのモデルでもIP68やIP67の防水性能を備えていることが多いです。
また、各メーカーのミドルレンジモデルに注目しましょう。
前述のAQUOS senseシリーズやXperia 10シリーズ、Google Pixel aシリーズ、Galaxy Aシリーズの一部など、手頃な価格帯ながらIP68やIP67の防水性能を持つ機種が増えています。
中古での購入を検討する場合は、バッテリーの劣化だけでなく、防水性能も経年劣化する可能性があることを念頭に置き、信頼できる販売店から購入するようにしましょう。
4. もしもの時のために スマホが水没した場合の正しい対処法
最新のスマートフォンは高い防水性能を備えていますが、それでも水没のリスクはゼロではありません。
万が一、大切なスマホが水没してしまった場合に備え、正しい対処法を知っておくことが非常に重要です。
焦らず、適切な手順を踏むことで、スマホが復旧する可能性を高めることができます。
4.1 スマホが水没したらまずやること
スマートフォンが水に濡れたり、水の中に落ちてしまったりした場合、時間との勝負になります。
以下の手順を落ち着いて実行してください。
1. すぐに水から引き上げる
水に浸かっている時間が長ければ長いほど、内部への浸水リスクが高まります。
可能な限り早く安全な場所へ移動させましょう。
2. 電源が入っている場合は、すぐに電源を切る
内部で通電している状態で水分が基板に触れると、ショートして致命的なダメージを与える可能性があります。
画面が消えている場合でも、スリープ状態の可能性があるため、強制終了などの操作はせず、まずは電源ボタンを長押しして正規の手順で電源を切ってください。
すでに電源が切れている場合は、絶対に電源を入れようとしないでください。
3. 表面の水分を優しく拭き取る
乾いたタオルや柔らかい布、ティッシュペーパーなどで、スマホ全体の水分を優しく丁寧に拭き取ります。
このとき、スマホ本体を強く振らないでください。 内部に入り込んだ水分がさらに奥へ広がってしまう可能性があります。
4. SIMカード、SDカードを取り外す
SIMカードトレイやSDカードスロットから、カード類を取り外します。
トレイの隙間から水分が侵入している可能性があるため、取り外すことで内部の乾燥を促し、カード自体の水濡れによる故障リスクも低減できます。
取り外したカードも、水分が付着していれば優しく拭き取ってください。
5. ケースやカバー、アクセサリー類をすべて外す
スマホケースやカバー、画面保護フィルムなども、水分が溜まりやすい箇所です。
すべて取り外し、本体の水分を拭き取りやすくし、乾燥を妨げないようにします。
6. 端子部分の水分を吸い取る
充電ポート(USB Type-C、Lightningなど)やイヤホンジャックなどの端子部分は、特に水分が残りやすい箇所です。
ティッシュペーパーをこより状にするなどして、優しく差し込み、内部の水分を吸い取ります。
息を吹きかけたり、綿棒などで強くこすったりしないでください。 水分を奥に押し込んだり、端子を傷つけたりする可能性があります。
4.2 絶対にやってはいけないNG行動
水没したスマホに対して、良かれと思って取った行動が、かえって状態を悪化させてしまうことがあります。
以下の行動は絶対に避けてください。
・電源を入れる、充電する
内部が完全に乾いていない状態で通電させると、回路がショートし、基板が修復不可能なほど損傷する可能性が極めて高いです。
「少しだけなら大丈夫だろう」という油断が、致命傷につながります。
完全に乾燥したと確信するまで、絶対に電源を入れたり、充電ケーブルを接続したりしないでください。
・スマートフォン本体を振る
水分を外に出そうとして本体を振ると、内部に入り込んだ水分が基板全体に広がり、被害範囲を拡大させてしまう恐れがあります。
水分は優しく拭き取る、または吸い取るようにしましょう。
・ドライヤーの温風で乾かす
早く乾かしたい一心でドライヤーの温風を当てるのは危険です。
スマートフォンの内部には熱に弱い精密な電子部品が多く使われており、高温によって部品が変形したり、故障したりする原因となります。 また、風圧で水分を内部の奥深くまで押し込んでしまう可能性もあります。
冷風モードであっても、風圧で水分を移動させてしまうリスクがあるため、推奨できません。
・冷蔵庫に入れる
低温で乾燥を試みようと冷蔵庫に入れるのは逆効果です。
冷蔵庫から取り出した際に、温度差によって内部で結露が発生し、新たな水濡れの原因となります。
・電子レンジで加熱する
絶対にやってはいけません。
スマートフォン内部の金属部品が火花を散らし、発火や爆発を引き起こす可能性があり、非常に危険です。 本体が完全に破壊されるだけでなく、火災や怪我につながる恐れもあります。
4.3 乾燥させる方法と注意点
水没したスマホの内部を乾燥させるには、時間と忍耐が必要です。
最も安全で推奨される方法は、風通しの良い日陰で自然乾燥させることです。 直射日光は避け、タオルなどの上に置いて、じっくりと時間をかけて内部の水分が蒸発するのを待ちます。
乾燥を促進させる方法として、食品用保存袋などの密閉できる袋に、スマートフォン本体と乾燥剤(シリカゲルなど)を一緒に入れておく という手段があります。
シリカゲルは、お菓子や海苔の袋に入っているものを再利用できますが、吸湿能力が落ちている可能性もあるため、新品を用意するのが確実です。
スーパーやドラッグストア、100円ショップなどで購入できます。
ただし、乾燥剤による乾燥で、内部の金属に錆ができてしまうこともあるので、注意&自己責任で実施するようにしてください。
生米にも吸湿性があると言われていますが、米の粉塵が端子部分に入り込むリスクも考えられるため、シリカゲルの方がより安全と言えるでしょう。
乾燥に必要な時間は、環境や浸水の程度によって異なりますが、最低でも24時間、できれば48時間~72時間(2~3日間)はそのままの状態にしておく ことが推奨されます。
内部の水分が完全に乾ききるには、想像以上に時間がかかるものです。
乾燥期間中は、絶対に電源を入れようとしないでください。 ここで焦ってしまうと、これまでの努力が無駄になる可能性があります。
4.4 水没したスマホの修理について 費用と依頼先
十分に乾燥させても電源が入らない、または動作がおかしい場合は、修理を検討する必要があります。
ただし、水没による故障は、基本的にメーカーの保証対象外となります。 AppleCare+などの追加保証サービスに加入している場合は、水濡れによる損傷も保証対象となることがありますが、サービス内容や免責金額を事前に確認しましょう。
水没修理の費用は、損傷の程度や機種によって大きく異なりますが、数万円以上の高額になるケースが一般的です。 基板の洗浄や部品交換が必要になるため、通常の故障修理よりも高くなる傾向にあります。
修理の依頼先としては、主に以下の選択肢があります。
- 契約している携帯キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなど):キャリア独自の保証サービスを提供している場合があります。
- スマートフォンメーカー(Apple Store、各メーカーのサポートセンターなど):正規の修理サービスを受けられます。
- 民間のスマートフォン修理業者:正規店よりも安価で修理できる場合がありますが、業者によって技術力や使用する部品の品質に差があるため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。改造扱いになるため通常の保証が受けられなくなったり、買取ができなくなるので注意が必要です。
修理を依頼する際には、水没した状況(いつ、どこで、どのような液体に濡れたかなど)を正直に伝えることが大切です。 正確な情報が、適切な診断と修理につながります。
残念ながら、損傷が激しい場合は修理不能と判断されたり、修理費用が新品の端末価格に近くなることもあります。 その場合は、機種変更を検討する必要も出てくるでしょう。
また、水没した場合、内部のデータが消失してしまうリスクが非常に高い です。
修理に出してもデータが復旧できる保証はありません。
データ復旧を専門とする業者も存在しますが、費用はさらに高額になる傾向があります。
4.5 事前にできる水没対策と備え
万が一の水没に備えて、日頃から対策をしておくことが重要です。
・データの定期的なバックアップ
これが最も重要かつ効果的な対策です。
スマートフォンのデータ(連絡先、写真、動画、アプリのデータなど)は、iCloud(iPhone)やGoogleドライブ/Googleフォト(Android)などのクラウドストレージサービスを利用して、定期的に自動バックアップを設定しておきましょう。 また、パソコンに接続して手動でバックアップを取ることも有効です。
データさえ無事であれば、万が一スマホ本体が使えなくなっても、新しい端末でデータを復元できます。
・スマホ用の保険や保証サービスへの加入検討
携帯キャリアやメーカーが提供する保証サービスの中には、水濡れによる故障に対応しているものがあります。
月額料金や修理時の自己負担額などを確認し、必要に応じて加入を検討しましょう。
・防水ケースや防水ポーチの活用
お風呂やプール、海、キャンプ、雨天時の屋外など、水濡れのリスクが高い場所でスマホを使用する場合は、信頼性の高い防水ケースや防水ポーチを活用するのがおすすめです。 ただし、製品の防水性能(IPX等級など)を確認し、使用方法を守って正しく装着することが重要です。
安価すぎる製品や、破損・劣化したケースの使用は避けましょう。
・ネックストラップやハンドストラップの利用
うっかり手を滑らせて水の中に落としてしまう、という事故を防ぐために、ストラップを取り付けるのも有効な対策です。
特に水辺での使用時には、落下防止策として役立ちます。
5. まとめ
スマホ選びで重要な防水性能は、IPX等級で確認できます。
等級の意味を知り、ご自身の使い方に最適なモデルを選びましょう。
ただし、IPX等級が高くても完全防水ではありません。
お風呂や海での使用、経年劣化には注意が必要です。
万が一の水没に備え、正しい対処法を覚えておくことも重要です。
このガイドを参考に、防水性能を正しく理解し、大切なスマホを水から守りましょう。